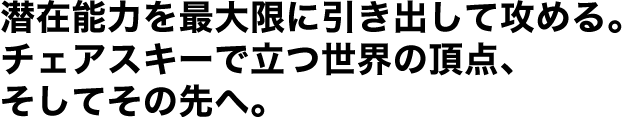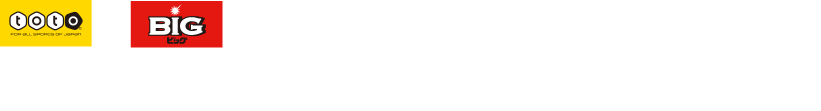![]()
――大日方さんは17歳でチェアスキーに出会い、その4年後の1994年にはリレハンメルパラリンピックに出場。さらに4年後の長野パラリンピックでは、滑降で金メダルを獲得しました。
チェアスキーを始めたのは高校2年生で、雪山を見るのも初めての体験でした。風を切る感覚を肌に感じると、「私は自由なんだ」という解放感を得ることができました。
リレハンメルは、「将来のための経験」という意味で、多少背伸びして出場させてもらえました。長野での金メダルも、その経験があってこそだと思います。
――日本のチェアスキーの、国際的な実力とは?
男子はアメリカ、カナダ、オーストリア、フランス、ドイツといった国々と互角で、世界のトップ3を争うレベルにあります。一方、女子は競技人口が男子に比べるとかなり少ないです。ナショナルチームは男子と女子に分かれているのではなく、1つのチームとして海外遠征などに出ているので、女子選手にとってはかなり苦労が多い環境だろうと思います。日本代表の今後を考えると、男女ともに若い選手をいかに発掘できるかが大事になりますね。
――競技を行う環境の面で、日本は他の国と比べて進んでいるのでしょうか? それとも遅れているのでしょうか?
チェアスキーの環境は、世界的に急速な成長期を迎えています。そのトップレベルに常についていくことの難しさを、各国が痛感していると思います。長野パラリンピックの頃は、世界大会は1シーズンに1回程度でした。それからワールドカップが始まり、徐々に試合数が増え、出場権は厳しく制限され、今では夏にも大会があります。日本は追いつこうとする努力は常に続けていますし、それに見合うような競技環境を得ていますが、相対的に競技のレベルが上がってしまっているので、決して日本が環境的にリードしているとは言えないですね。
また日本の選手は、費用の負担、練習場所の確保、仕事と競技の両立などが、競技を続けるうえでの課題になっています。一方、カナダやイギリスなどは、大学がトレーニングの拠点になっていて、幅広い年齢のパラリンピック選手を大学が受け入れているようです。
――パラリンピック自体の在り方や意義について、大日方さんはどのような見解をお持ちですか?
私は、パラリンピックには、「できない」という思い込みを、「できる」という現実に変える力があると思っています。人は、無意識のうちにあきらめてしまうということがあります。「もうできないな」と、あきらめることを繰り返していくうちに、可能性はどんどんしぼんでいってしまうものです。
私自身、子どもの頃は、スキーとは立って滑るものだと完全に思いこんでいました。けれど、そうじゃなかった。立てなくてもチェアスキーがあるのです。一見不可能なことも、本人の努力や道具を工夫することなどによって、可能になる。これは、パラリンピック全体として社会に伝えることができる、強いメッセージだと思います。
――パラ・スポーツ(障がい者スポーツ)を見る人、支える人たちには、どういうことを意識してほしいですか?
まず、現場を見に来てほしいです。写真だけで見るとか、話だけで聞くとかよりも、競技場に足を運んで実際の競技を見ていただくと、迫力が感じられると思います。2014年の11月には、東京でブラインドサッカーの世界選手権が行われました。観戦に訪れた多くの人は、スピードと迫力に驚いたことでしょう。選手たちは全力で走り、不意に体がぶつかり合う。そして、力強いドリブルと正確なパスを駆使した戦術実行力。あの難しさ、あの勇気は、一度見たら「すごい」と感じていただけると思います。
そして、パラ・スポーツを見る時、どうしても「ない」部分に注目が行きがちだろうと思いますが、私たちはぜひ、「ある」部分に注目していただきたいと常々思っています。例えば片脚でスキーを滑る選手がいたら、「なぜ彼は(彼女は)片脚を失ったのか」というのはバックストーリーとして興味深いのですが、見ていただきたいのは、残っている片脚のたくましさなのです。残っている部分をいかにフル活用しているのか。現在のパフォーマンスにたどり着くまでに、どれだけの努力を積み重ねたのか。人は何かを失ったとき、残っている自分の潜在能力が目を覚ますものなのだろうと思います。眠っている力をどれだけ引き出して競技に臨むか、という点に、ぜひ注目していただきたいですね。
――パラ・スポーツ界にとって、totoの助成は、どのような効果をもたらしていると感じますか?
人数だけを見ると、障がいのある人のスキー人口は、多いとは言えません。けれど、個々にとって、一つひとつの体験は非常に価値のあるものです。障がいのある人と、スポーツとの最初の出会いを、普及のイベントによって作る。それによって、人生そのものが豊かになる。そういった意味で、普及事業というのは非常に重要だと思います。特にスキーの場合は、障がいを持つ人にとっては気軽にホイと行けるものではありません。totoの助成を通した普及事業を、何カ月も楽しみに待っているという人も、たくさんいます。そういう人たちの気持ちを、ちゃんとフォローしてあげられる、totoの助成は非常に重要だと考えています。
――最後に、totoを購入しているスポーツファンに、メッセージをお願いします。
勝負の世界という意味のスポーツばかりでなく、生涯スポーツ、ジュニアのためのスポーツなど、スポーツの楽しみ方には、多様性があります。それらのどのステージでも、第一歩にあたるのが、totoを購入してくださるみなさんの行動にあると、私は考えています。実際、私たちは助成をいただいている立場にありますが、みなさん自身が利用しているスポーツ施設などが助成を受ければ、みなさんが恩恵を受ける側にもなります。totoは、スポーツを応援する輪を広げていく大きな推進力になっています。totoを購入することで、多様なスポーツの楽しみ方を応援していただき、ありがとうございます。
![]()
――狩野選手がチェアスキーと出会ったのは、いつですか? そのとき、どのようなことを感じましたか?
北海道生まれの僕は、スキー指導員の父のおかげで、小学5年生のときに初めてチェアスキーで滑りました。その翌年、1998年にテレビで長野パラリンピックを見ました。パラリンピックという大会があること自体もその時に初めて知りました。僕は、チェアスキーが競技スポーツとして存在することに衝撃を受け、選手たちの迫力に圧倒され、僕の人生は変わりました。「自分もチェアスキーで世界を目指したい」と、強く思ったからです。
――狩野さんは2010年のバンクーバーパラリンピックで金メダル1つ、銅メダル1つ、2014年のソチパラリンピックでは金メダル2つを獲得しています。メダルを取った種目は、スーパー大回転と滑降で、いずれもアルペンスキーの中ではスピード系に分類される種目ですね。
自分の滑りのスタイルが、スピード系の種目に向いていたのだと思います。僕のスタイルというのは、ガンガン攻めるスキーです。滑降では、最大時速130kmぐらい出します。競技者としてチェアスキーを始めた当初は、飛ばせるだけ飛ばして、結局ミスしてコースを外れてしまうことも、しばしばありました。しかし、その滑りを見た当時のコーチが、高速で攻める僕のスタイルをポジティブに評価してくださり、「技術と経験が備われば、いつか世界を取れる」と期待をかけてくれました。
――雪山という大自然が舞台で、コースごとの特性、当日の天候や雪面のコンディションなどは毎回変化すると思います。安定したパフォーマンスを発揮し続けるには、どのような工夫が必要ですか?
僕は一度滑ったコースの景色や旗の位置、雪質、スピード感などを本当に細かく記憶します。パラリンピックの前年には必ず現地でプレ大会が行われ、パラリンピック本番と同じコースを滑るのですが、ソチまでの一年間は、事あるごとにその記憶を引き出しながら、頭の中でいろんなレース展開をシミュレーションし続けていました。その甲斐あって、パラリンピック本番当日に雪面のコンディションや、トップの選手のタイム、または「他の選手がどこでミスをした」などの細かい情報が入ってくるたびに、すぐにレースプランを微調整することができたのです。
――健常者スキーヤーと、滑りの技術について情報交換することはありますか?
僕らが動かせるのは上半身のみで、言ってみれば腰から直にスキーがついているというイメージですので、腰とチェアスキー・フレームをいかに一体化できるかが大事です。そのためには体幹、上肢、バランス感覚など、残存機能を総動員して、スキーをコントロールしなくてはなりません。
その中で、やはり健常者の滑りはヒントになります。健常者の足裏の感覚に当たるものを、どうやってフレームで表現するのかということを、常に考えています。逆に僕らが、健常者にヒントを与えることもあると思います。チェアスキーヤーは健常者に比べて、足首と膝、関節が2つ少ない状態ですから、よりシンプルにスキーを操作しているといえます。実際、ここ数年は健常者のトップレーサーズキャンプに、僕たちチェアスキーヤーも参加させていただいたりして、お互いに刺激を与え合えていると思います。テクニックの情報交換ももちろんですが、チェアスキーをスポーツとして見ていただくためにも、健常者と合同で活動することは、僕らにとってとても意味があると思います。
――狩野さんの年間スケジュールは?
10月から3月まではナショナルチームの一員として、海外で20レース前後、国内で4レースぐらいに出場します。ナショナルチームの活動がない夏場は、南半球で、仲間たちとホテル代や車代などを出し合って、合同合宿をしています。
オフシーズンにはしっかり体づくりをします。ウェイトトレーニング、持久力トレーニング、バランストレーニングや体幹の強化など、さまざまなことをやりますね。
――パラリンピックは、回を重ねるごとに、より高度なスポーツ大会として先鋭化されているように感じます。狩野さん個人としても、日本チーム全体としても、国際競争力を維持していくためには、どのようなことが必要でしょうか?
3つの観点があります。まずはトレーニング環境。日本国内には、滑降の練習をできる場所がほとんどありません。健常者の大会も、日本では約20年も開かれなかったぐらいです。カナダやアメリカには滑降専用のコースがあり、普段から高速トレーニングができる一方、日本の選手は海外で行われる大会前日の公式トレーニングだけというのが現状です。
次に、用具の開発です。フレームと呼ばれる、マシンのメインとなる機構は、実は日本の製品が世界でもっとも高いシェアを得ています。しかし近年は、僕たちアスリート側が、開発者の想定を越えた身体能力を発揮し始めています。つまり今は、チェアスキーという競技の発展に、ものすごく加速がついている時期でもあるので、より人間の可能性を引き出せる用具の開発が求められています。
そして3つめの観点は、次世代の選手の育成です。日本においては、3つの課題の中でこれがもっとも急務でしょう。僕らが持っている経験や技術を、できるだけ多く伝えたいのですが、競技人口がなかなか増えていきません。海外の例ですと、ドイツやオランダなどは、まだ競技に本腰を入れていない中学生などもソチに連れてきて、目の前で競技を見せていました。世界最高峰の滑りを目に焼きつけさせて、本人のやる気と意識を高めようという狙いが見て取れたので、うらやましいと思うと同時に、日本からはそのような若い子が来ていなかったことを残念に思いました。
――次世代の選手育成に、totoの助成が果たす役割として、どのようなものが期待されますか?
totoの助成によってチェアスキーの普及活動が行われています。多くの人たちに障がい者スポーツを身近に感じていただき、「面白い」「カッコイイ」と思っていただくきっかけを作るという意味でも、totoの助成が果たす役割は大きいと思います。「障がい者なのにスポーツをやっていてすごいね」ではなく、純粋に「チェアスキーって面白いスポーツだね」と思ってもらえることが、僕らの願いです。
その点、2020年のオリンピック・パラリンピックが東京にやってくることは、大きなチャンスだと思っています。障がい者スポーツに抱くみなさんのイメージが、あと5年で大きく変わるのではないかと期待しています。そして、パラリンピック選手としての僕個人の理想は、パラリンピックとオリンピックが、一つの大会になることです。開催期間が長くなったり、選手の数が増えたりするので、実現に向けて数々の課題があることは理解できますが、同じ大会の中に健常者の部と障がい者の部があるというふうになれば、世の中はもっとよくなるのではないかと思っています。

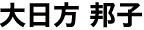
- おびなた くにこ
1972年4月16日生まれ、神奈川県出身。3歳の時に交通事故により右足切断、左足に重度の障がいを負う。高校2年よりチェアスキーを始め、1994年リレハンメル大会からパラリンピックに5大会連続出場し、2個の金メダルを含む10個のメダルを獲得。日本障害者スキー連盟 常任理事、日本パラリンピック委員会(JPC)運営委員、日本パラリンピアンズ協会副会長。


- かのう あきら
1986年3月14日生まれ、北海道出身。小学校3年の時に交通事故により脊椎損傷。中学1年より本格的にチェアスキーに取り組み、2006年トリノ大会からパラリンピック3大会連続出場。2010年バンクーバーでは男子座位スーパー大回転で金メダル、男子座位滑降で銅メダルを獲得。2014年ソチでは男子座位スーパー大回転と滑降で金メダルを獲得。